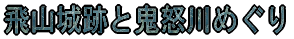
No. 82 2007年12月 (2001年1月 開設)
ここには次のページをリンクしています。
・飛山城跡を歩く
33. 芭蕉門弟句碑


|
芭蕉(1644-1694)には、多くの門弟がいて、俳聖と呼ばれるほど、後継者を残した。奥の細道で同行した曽良も、日光で句を詠んでいる。男体山の黒髪山は、霞かかりて雪いまだ白し、
剃捨て黒髪山に衣更 曽良
この句の碑は、見当たらない。日光から黒羽に辿る途中に詠んだという、「かさねとは八重撫子の名成るべし」の句碑はいくつも残り、大田原市にかけて、親しまれているのに比べ、なんとも寂しい。
日光の市街から稲荷川を渡った萩垣面にある興雲律院の道の対面に、ホテル高照と旅館梅屋敷がある。梅屋敷の入口に、石の「梅やしき、松やしき」の道標があり、まっすぐ下ってゆくと、松屋敷の門に出る。松屋敷は、金谷ホテルの別荘だったというが、朽ちて崩壊が進んでいる。庭園は、それでも面影が残り、池を巡って石灯籠や植栽が美を添えている。門の辺、大小の自然石があって、小さな方(写真上)に道標が刻まれている。「右 大日堂、左 含満」、右側面に「宝暦十三未葵歳」(1763)、そして裏面に、
雨晴れて 水清けさや 大谷川 紀文
紀文は、紀伊国屋文左衛門、享保19年(1734)没の江戸中期の豪商で知られる。紀州からみかんや塩鮭を船で江戸に運び、江戸の大火では、木曾の木材を売って巨万の財を成した。俳句は、芭蕉や其角に師事し、没後に建立されたこの句碑は、大谷川の辺にあったものと思われる。
梅屋敷の前の池のある庭園には、
夕桜 おしまれね身に 散りかかる
其角堂永機
の大きな句碑(写真下)が見つかる。永機は、其角の門流を継ぐ其角堂七世、明治37年没。建立明治19年のこの碑の近くには、桜の大木があったという。
萩垣面には、律院の山門、本堂などのほか、明治の洋画家五百城文哉の旧居とロックガーデンや墓など見所が多い。 |